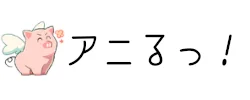評価 ★★★★★(88点) 全102分
あらすじ 大自然に覆われた無人島に流れ着き、偶然にも起動ボタンを押されて目を覚ました最新型アシストロボットのロズ。引用- Wikipedia
全ての親に捧ぐ
原作は児童文学な本作品。
監督はクリス・サンダース、制作はドリームワークス・アニメーション
お手伝いロボット
見出して感じるのはコミカルな動きの表現だ。
制作のドリームワークス・アニメーションは
シュレックやボス・ベイビーなどで有名な制作会社だが、
そんなドリームワークスらしい動きの表現に目を奪われる。
この作品の主人公は「お手伝いロボット」のロズだ。
近未来の世界で高度なAIを搭載したロズは人間のために仕える存在だ。
しかし、そんな彼女は無人島に流れ着いてしまう。
そこには仕えるはずの人間がおらず、動物しか居ない。
ありとあらゆる言語で仕事はないか?と問いかけても言葉すら通じない。
自らの存在意義、誰かのために何かを手伝いたい。
そんなロズが自ら「動物の言葉」を時間をかけて学習することで
動物たちがコミカルに喋りだす。
動物が人間の言葉を喋るというのはディズニー映画を筆頭に
アニメではよくあることだが、そのあたりのファンタジーをきちんと設定付けている。
だが、言葉を覚えたところでロズの見た目はロボットだ。
自然の中で生きる動物たちにとっては異物でしかない、
他の動物を襲うわけでもなく、かといって機械の体は餌にすらならない。
野生の島ではロズは恐れられる異型の「怪物」だ。
そんな中で彼女は1話の「鳥」と出逢うというところから物語が始まる。
刷り込み
ロズが拾ったのはガンという鳥の卵だ。
生まれたばかりの雛は彼女のことを「母」と勘違いしてしまう。
そんなガンの雛こと「キラリ」を育てることが彼女の仕事だ。
ロボットとしてプログラムされた使命にようやく従うことができる。
こうやって簡単に序盤のあらすじを書いていくと、
これを読んでいる多くの人が「先の展開が読めるな」と想像するはずだ。
それは半分正解で、半分不正解だ。
いわゆる「AIの自我の目覚め」という普遍的なテーマを描いている部分もあり、
想像通りの展開もある。
しかし、この作品の主題は「子育て」であり「本能」だ。
ロズが拾った鳥の卵には本当の親や兄弟がいる。
だが、そんな親や兄弟をロズはクマに追いかけられた結果
「潰して」しまっている。
シンプルにえぐい(苦笑)
「キラリ」にとってロズは本当の両親や兄弟を殺した存在だ。
ロボットであるロズにとっては罪悪感などない、
彼女には誰かを傷つけることは本来はできず、あくまで事故だ。
そこにさらに「キツネ」の「チャッカリン」が
ある意味父親代わりで二人の間に入ってくるものの、
「チャッカリン」も最初はキラリの卵を「くおう」としたキツネだ。
本当の親を殺した「ロボット」の母と
自分をくおうとした「キツネ」の父、
それを知らずに「キラリ」という鳥は育っていく。
あまりにもえぐい設定にこの先どうなってしまうんだろうと
自然と身を乗り出してしまう。
自然界の描写も素晴らしく、コミカルに動物を描きながらも
そこには「弱肉強食」の世界が広がっている。
いつ食われるのか、いつ死ぬのか、わからない。
動物の世界において他者を傷つけることは生きるためでもある。
それをこの作品では自然と描いている。
ブラックジョーク的なものまで含まれつつも、
コミカルな動きのおかげで子供が見ても大人が見ても
楽しめる作品に仕上がっている。
プログラム
ロズはあくまで「人間」の手伝いをするロボットだ。
人間の子供ならいざしらず、動物の子育ては彼女のプログラムにはない。
学習する資料があるわけでもネットに繋がるわけでもなく、
彼女にとってはキラリの子育ては予測できないことの連続だ。
「キラリ」はガンという渡り鳥だ。
冬までに飛べるようにして温かいところに
飛び立たせなければ死んでしまう。
彼女の任務はキラリを泳げるようにし、飛び立たせることだ。
しかし、ただの食事でさえロズだけではどうにもならない。
彼女の中には「ガン」という鳥が何を食べるのかという情報がない。
プログラムに従ってもキラリを育てることはできない。
これは人間の子育てにも言えることだ、育児書や
最近では子育てYouTubeなど色々とあり、子どもが生まれる前に学ぶことは多い。
だが、実際に子どもが生まれると、そんな学習した情報にはない
予想外なことの連続だ。子育ては「論理的思考」では行えない。
ロボットであるロズにとっては困難な道程だ。
しかし、そこにはロズだけではなくチャッカリンもいる。
嘘ばかりで憎まれ口を叩くキツネではあるものの、
彼は「孤独」なキツネだ。
ロズやキラリと暮らすうちに彼も変わってくる、
名付け1つとってもロズにとっては難しいことだ。
自身は「ロッザム」という製品名であり、「製造番号」がある。
だが名前はない。名前がない彼女が他者に名前をつける、
論理的思考ではない、プログラムを超えた思考をしなければ
名付け1つできない。
一生懸命、ガンの雛をみつめ、「キラリ」という名前をつける。
この工程だけでもうちょっと涙腺を刺激されてしまう。
本来動物というのは本能に従うものだ。
キツネにとって鳥の雛など本能の前では餌に過ぎない。
ロズにとっても鳥の雛を育てるということは
「プログラム」という名の本能にはないことだ。
だが、キツネもロボットも必死に
自身の本能やプログラムにはないことをしようとしている。
論理的な思考でも本能でもない「なにか」が二人にはある。
動物の本能というものをある種のプログラムに例えるのは
この作品の面白いところだ。
遺伝子に刻まれた情報から生まれる本能は
確かに生物にとってはプログラムなのかもしれない。
真実
キラリはガンのなかでも小さい子だ。
同じ年代の子と比べても明らかに小さく、
泳ぐのにも飛ぶのにも苦労している。
野生においてそういった「異物」は群れに入ることはできない。
まして親はロボットと狐だ、ガンにとっては異質すぎる存在だ。
そんな中で「キラリ」が自らの出生の秘密を知ってしまう。
本当の両親をロズが殺してしまっていることを。
非常に重苦しい展開だ、シリアスではある、
だが、そこでもこの作品らしい展開があるからこそ
この作品は名作足り得る。
キラリの両親は確かにロズが踏み潰してしまっている。
彼の兄弟も同じく卵の状態で踏み潰し、
唯一残ったのがキラリの卵だ。
そんなキラリをロズは育てて大きくなったものの、
本来は恨むべき相手だ。
だが、成長したからこそキラリは普通のガンよりも
「未熟」であることがわかる。
野生の世界において弱者は捨てられる運命だ。
ロズとチャッカリンが彼を守ったからこそ大きくなれた。
もし、ロズがキラリの家族を踏み潰さなかったら
キラリはどうなっていただろうか。
野生の世界で野生の動物にキラリは生きたまま
今のように育っただろうか
仮定の話でしかないものの、野生の厳しい部分だ。
ロズが家族を踏み潰したからこそ、キラリは大人になれた。
踏み潰していなかったら雛のときに死んでいたかもしれない、
食われていたかもしれない。
今のキラリがあるのはロズとチャッカリンのおかげだ。
複雑な心境を抱えつつも、キラリは自分に飛ぶ訓練をしてくれる二人に
また心をひらいていく。
ロズもまた変わっている、自分の中のお手伝いロボットとしての
プログラムを切り、自らが思考し、子育てをしてきた。
自分の中に生まれている「感情」と呼べるものに彼女もまた戸惑っている。
ロズの体はボロボロだ、島についた時点でいくつかパーツを失い、
キラリを育て守る中で「足」も破損している。
子どもはどんどん大きく成長し立派になっていくのに、
親はどんどんぼろぼろになって年老いていく。
ロボットでありながらまるで年を取っているように見せる過程が
親心を刺激されてしまう。
豊かなアニメーション表現が暖かくも美しく、
特に「すだち」のシーンは印象的だ。
巣立ち
ロズはロボットではあるものの飛ぶ機能を持ち得ていない。
自分にできる最大限のことをしても、キラリとともに飛び立つことは
彼女にも、狐であるチャッカリンにもできないことだ。
親が届かないところに子どもはいつか行ってしまう、
それが大人になることであり親離れだ。
キラリがいつものようにロズの肩にのり、
そこから仲間たちとともに飛びだっていく。
たったこれだけのシーンなのにもう大号泣だ。
ロズは羽のように腕を広げ、島のギリギリまで彼を見送る。
ロズが事故でキラリの家族を踏み潰していなければ、
キラリは渡ることなどできなかった、ここまで大きく育つことなど無かった。
最大限の愛情を、論理的思考を超えた「愛」をもって育てられたことを
実感させてくれる。
「お願いします、私の息子。キラリのことを」
ロズは託すことしかできない、彼女はガンではない。
種族が違う家族にはそれぞれの居場所がある。
キラリは渡り鳥として冬は暖かい場所へわたり、
キツネのチャッカリンは冬を越えるために穴に潜り、
ロボットであるロズは
「お手伝いロボット」として元の場所に戻らなければならない。
それぞれの居場所がある、だが、ロズには居場所がない。
元の場所に戻ることもできる、しかし、彼女にとっての居場所は
もうこの島だ。「親」になってしまったからこそ、
子どもが帰るまでこの島に居たい。
子どもが親離れするように、親も子離れしなければならない。
しかし、ロズにはそれができない。
終盤
終盤の展開はやや慌ただしい。
厳しい冬を乗り越えるためにロズは島の動物を助けて回る、
彼女を化け物とよんだ動物もいる、いたずらしてきた動物もいる、
おそいかかってきた動物もいる、しかし、彼らが協力してくれたからこそ
ロズはキラリを育てることができた。
自分にできない空の飛び方をキラリに教えてくれた動物もいる、
自分にはできない子育てのやり方を教えてくれた動物もいる、
自分の足を直してくれた動物もいる、
そんな恩義に報いるかのようにボロボロの体で助けて回る姿に
もうただでさえ弱っている涙腺がズタボロだ。
一箇所に集められた動物たちの中には食うものと食われるものが居る。
だが「生き残る」ためには共存しなければならない。
ロズが助けてくれたからこそ彼らは生きている、
「食欲」という動物たちの中にある本能、
そんな本能を超えて彼らは冬の間だけ休戦協定を結ぶ。
この作品は徹底的に「本能」というものを描いている。
我々人間も含め動物には本能がある、
誰に教わらずとも何を食べれば良いのかがわかり、
誰に教わらずとも子孫繁栄していく。
それが動物たちのDNAに刻まれたプログラムという名の本能だ。
しかし、生きていくためにはその本能をときおり超えなければならない。
論理的思考、理屈ではないことがときに求められる。
それは人間も同じだ。
理屈ではない自己犠牲、誰かを守るために、自分よりも大切なものを
守るために自分の命すら投げ出すことがある。
それは本来、本能から外れた行為だ。
生きるという本能を超えても守りたいものがある。
本能だけに従うなら愛情などいらない、
子孫繁栄という動物の本能だけに従えば良い。
だが、人間も動物にも本能を超えた先の「愛」がある。
それをロボットというものを通して描いているのがこの作品だ。
総評:こんな名作を埋もれさすな!
全体的に観て素晴らしい作品だ。
テーマとしては「親子愛」と「AIの自我の目覚め」という
普遍的なものでしか無いのだが、その王道ともいえるテーマを
きちんと掘り下げ、盛り上げる設定とストーリーラインがあり、
序盤から中盤までそれを丁寧に見せてくれている。
ドリームワークス・アニメーションらしいアニメーションも素晴らしく、
かつてのディズニーのようなコミカルな動物の描写があるとおもえば、
リアルなロボットの描写もあり、無人島の美しい景色は
時折目を奪われるような描写になっており、
ストーリーを盛り上げてくれる。
終盤の展開はあえてネタバレしないものの、
ややご都合主義や引っかかる部分がないと言えば嘘になる。
序盤から中盤、巣立ちまでの展開と比べて終盤の脚本はややあらが目立つ
部分もあり、中盤までなら100点、中盤から終盤にかけて
60点なストーリーになっていった印象だ。
しかし、ご都合主義でも物語はハッピーエンドのほうがいい。
まで観ていない人はぜひ、劇場に足を運んでほしい作品だ。
個人的な感想:刺さりまくった
おそらく私はこの作品が刺さりすぎている。
この作品で描かれている内容が私の今の状況とかぶるものがあり、
そのせいで深くこの作品が刺さりすぎてしまった。
本当に個人的なことになるが、
ちょうど去年、第一子が誕生しており、いわゆる未熟児で生まれている。
それが作中の「キラリ」と重なる部分が多く、
序盤を過ぎたあたりから「あ、やばいな」と思いつつも
涙を止めることができなかった。
必要以上に私が刺さりすぎている部分はあるものの、
同じように子どもが居る方には刺さる作品のはずだ。
是非、劇場でご覧いただきたい。