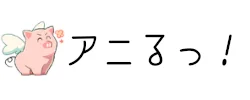評価 ★★★★☆(69点) 全90分
あらすじ 現在より少しだけ先の未来。人々の生活をサポートするロボット「ソルト」を開発・製品化することに成功した17歳の天才科学者・水溜明は、新たな発明が失敗続きで行き詰まりを感じていた。引用- Wikipedia
狂気のSFサイコスリラー
本作品は劇場アニメオリジナル作品。
監督は安田現象、制作は安田現象スタジオ by Xenotoon。
安田現象氏はアニメーション作家としてYouTubeなどで
ショートアニメを多く公開しており、本作品は
8人で作られたという少数精鋭な作品だ。
なお、本レビューにはネタバレが含まれます。
近未来
この作品の序盤は独特のとっつきにくさがある。
その原因は主人公だ、高校生である主人公は授業そっちのけで
自分の研究に没頭しており、学校だろうが構わずに
自分の研究をおこない、大爆発を時に起こしたりもする。
彼は天才的な技術者であり、この世界の街中には
彼が開発した「ソルト」というお手伝いロボットが
当たり前のように存在し、人々の生活を助けている。
だが、そのロボット自体は彼の亡くなった母が残した研究の一端でしかなく、
彼自身はその再現をしようと思ってもできないでいる。
ソルトのパワーアップ、ソルトの合体変形、不死の生命体。
だが、不死の生命体はあっさりと死んでしまい、
ソルトのパワーアップも合体変形も無し得ていない。
天才的な母が唯一生み出した失敗作が自分だと自負するほど
彼は追い込まれている。
そんな彼を慕う「可愛いクラスメイト」などもいるものの、
彼女の気持ちなど一切察しておらず、友情や恋愛よりも
研究の成果を出そうと必死だ。
どこか人間性がなく、サイコパスとまではいわないものの、
社会不適合者なのが本作品の主人公だ。
長い間、いろいろな研究をしているのにうまくいかない。
行き詰まっている彼は友人の言葉につき動かされる
「彼女を作ればパワーアップできる」
高校生の軽いノリだ、本当にパワーアップできるわけはないのだが
主人公はそんな言葉を信じてしまう。
だが、彼の受け止め方は少し違う。
友人は彼女を「作れば良い」といった。
しかし、彼の頭の中で「創る」という言葉が
「創る」言葉に変わっている。
この作品はこういった「言葉遊び」が非常にうまい。
高校生が彼女を作って青春を謳歌する、
そんな普通の物語ではなく、この作品は
高校生が彼女を創ってしまうところから物語が始まる。
Aiもの
この作品の序盤はとにかくとっつきにくさがない。
感情移入しにくい主人公もそうだが、
主人公があっさりとアンドロイド「0号」を創り上げたかと思えば、
次のシーンでは主人公と同じく学校に通っており、
それをクラスメイトなども当たり前のように受け止めている。
この世界でアンドロイド自体は当たり前に存在するわけではない、
もう少し周囲が驚いても良いようなものだが、
あっさりと受け入れられ、「0号」は主人公の彼女として行動していく。
彼女になるためにはどうすればいいのか、そもそも恋人とはなにか。
生まれたばかりの0号が少しずつ成長していく過程が描かれている。
この序盤の展開は古今東西、AIを題材にした作品では
腐る程やったテーマだ。
AIに感情はあるのか、自我とよべるものはあるのか。
そんなありきたりかつ普遍的なテーマが描かれる。
「アイの歌声を聞かせて」など
AIをテーマにした作品はアニメ映画でも多くあり、
序盤はあまりこの作品らしい面白さがわかりにくい。
アニメーションのクォリティは非常に高い。
フルCGのアニメではあるものの、それを感じさせないような、
きちんとした「アニメ調」、いわゆるセルルックCGになっており、
優秀なキャラクターデザインもあってCG特有の欠点も感じにくく、
フルCGでありがちなキャラの無駄な揺れなどもない。
そうかとおもえば、時折フルCGだからこその
大胆なカメラワークを見せることもあり、
少数精鋭で創ったとは思えないほどにアニメーション部分での
クォリティは大手のアニメ制作会社に負けないものになっている。
愛情
この序盤、いや、冒頭のシーンからこの作品は
きちんと終盤に向けての伏線をばらまいている。
はっきりいってわかりにくい部分もある、
90分ほどの尺しか無いというのもあるのだが、
あえて「言葉」で説明していないことも多い。
冒頭のちょっとしたシーンが重要な伏線になっていたり、
少しの「変化」が終盤の展開への伏線だ。
「0号」は序盤であっさりと人間性を手に入れ、
主人公への思いをきちんと自覚する。
0号は主人公の「恋人」として作られた存在だ。
そうなるように作られているからこそ、好きになって当然だ。
だが、彼女はそんなプログラムを超えた感情を
言語化できない思いを自覚していく。
しかし、主人公はそれを理解できない。
パワーアップできるはずだったのに研究はうまくいかず、
パワーアップできるはずだったのに研究の邪魔ばかりする。
彼にとって母の研究を再現し、母の研究を引き継ぐのが
存在理由のようなものだ。
それができないことへの苛立ち、
パワーアップできるはずの存在の彼女「0号」への
理解できない思いもまた彼を焦らせる。
幼い頃に母が死に、彼はずっと孤独な存在だ。
「家族」というものを「愛情」というものを彼は知らない。
だからこそ、彼は0号を突き放す。
自らがそう創ったのに、自らのそばにいるように創ったはずなのに
彼は自らの子どもとも言うべき存在を突き放してしまう。
当然、0号はそれを拒否しようとするものの、
彼女にはそれができない。創造主の「命令」は絶対だ。
それに逆らうことは「死」を意味する、そう作られている。
そんな命令に逆らうことのできない彼女の中にも疑問が生まれる。
自分の中の思いは本当に本物なのか、この感情は作られたものなのか。
主人公に突き放されたことで彼女の存在理由も揺らいでしまう。
とてもじゃないが主人公に感情移入することもできず、
ドロドロとした中盤だ。
おそらくキャラクターの感情や行動理由が
理解できないという人も多いかもしれない。
それはこの作品があえて「言葉」にしていないからだ。
だからこそ理解できない、わからないという人が生まれ
各種レビューサイトなどで賛否両論になることもわかる。
だからこそ、私はあえてここでネタバレという名の
決定的なことを書き記す。
創造主
終盤で「主人公」もまた作られた存在であることが明らかになる。
これはあえて言葉や台詞として出てくるものでもなく、
映像としてもややわかりにくい表現になっている部分がある。
例えば冒頭の1シーン、主人公が研究をしていた部屋で
過去に主人公の母が「なにか」に「いきなさい」と
いいかけているシーンが有る。この「なにか」こそ主人公だ。
主人公が「0号」を創り上げたように、
主人公の母もまた「主人公」を創り上げている。
0号と違うのは「誰かを愛する」ということを命じられておらず、
彼に命じられたのは「いきなさい」という言葉のみだ。
行きなさいではなく、生きなさい。彼は生きることを命じられている。
第三の人類とも呼ばれる主人公や0号の存在は
主人公の母の研究の成果そのものだ。
0号を創ることもまた母の予想通りなのだろう。
「一人」では孤独だ、しかし、母自身は病に蝕まれ時間がない。
永遠に生きる存在である主人公のそばにいることはできない。
ならばどうすればいいか、同じ存在を主人公が作ればいい。
それが0号だ。
全ては「母」たる創造主の手のひらの上だ。
それを終盤で主人公は内面世界という名の
「母の記憶」との対峙で理解する。
自分は失敗作ではなかった、母の期待に添えることができた。
母の愛をしり、自らの中にある愛も自覚することで
彼自身が「パワーアップ」する(笑)
アクション
この終盤の展開はやや唐突かつわかりにくい部分が多く、
主人公自身もまた人造人間であるということがわからなければ
理解できない部分でもある。
しかも0号がさらわれたかと思ったら、
それを追いかけるためにアクションシーンが展開する。
彼がずっとつけていたゴーグルのようなもので0号の位置を
特定し、研究の成果である合体ソルトに乗って
さらわれた0号を追いかけるシーンはどこどの探偵小僧を
思い出すようなスケボーアクションだ(笑)
映画としての盛り上がりが欲しかったというのはわかるが、
この終盤のアクションシーンはかなり唐突な感じも強く、
ソルトの合体やレースアクションなどアニメーションとしては
しっかりとした見ごたえはあるものの、唐突な感じ強い。
誘拐犯もどこぞの黎明卿のような格好をしており、
安田現象監督が好きな作品の要素なのかもしれないが、
エヴァ的なデザインのUIだったり、コナンみたいなアクションだったり、
メイドインアビスのキャラに似ていたり、
ところどころオマージュなのかリスペクトなのかよくわからない要素がある。
そのあたりは気になるものの、すべてを吹き飛ばすのが終盤だ。
愛の証明
誘拐事件に関してはあっさりと解決してしまい、
犯人自体もどこかへ行ってしまうという有耶無耶な感じになっている。
このあたりのストーリーのたたみ方は雑に感じるものの、
それ以上の展開が終盤待ち受けている。
母の愛を理解したことで、自身の中の愛を自覚し、
0号の愛を受け止めようとする主人公だが、
主人公はすでに0号を突き放し、命令までしてしまっている。
だからこそ、彼女の中には迷いがある。
自分の思いは本当なのか、それとも作られた偽物なのか。
それを彼女は証明しようとする。その証明をするにはどうすればいいのか。
普通のこの手の作品ならアンドロイドが流せない涙を流したり、
プログラムにはない行動をしたりすることで、
AIやアンドロイドの「人間性」を証明しようとする。
だが、この作品は違う。
この作品では創造主に対して「危害」を加えることは基本できない。
ロボット三原則のようなものだ、それをしようとすれば
自分自身にも痛みが襲い、最悪、自我が崩壊する。
そんなルール、作られたものだからこそ存在するものを彼女は越えようとする。
愛情は時に互いを傷つけ合うこともある、好きだからこそ相手とぶつかり、
自分の思いを理解してもらおうと言葉や、時には暴力で
傷つけ合うことで「愛」を証明しようとする。
0号の行動はある意味理にかなっているものの見た目は完全にホラーだ(笑)
主人公を殴り、切りつけ、刺しまくる、
自分自身にも痛みが襲い、自我が崩壊しそうになっても、
自分自身が作られた存在ではない、自分の中の思いは本物だということを
証明するために主人公を殺そうとまでしてくる。
とんでもない映像と怒涛の展開に圧倒されて笑うしかできない。
エンドロール
狂った愛の証明方法だ。だが、彼女は「作られた存在」だ。
主人公を傷つけることはできても、殺すことはできない。
彼女は長い長い眠りについてしまう。
ラストは彼女が目覚めて終わる。
これでハッピーエンドになれば普通の作品だ。
だが、この作品はそんな普通の作品ではない。
「怪作」だ。
終盤の唐突なサイコスリラー展開もそうだが、ラストに関してはホラーだ。
主人公は「母の記憶」が保存されたデバイスをずっと持っており、
その記憶を解析することで多くの研究成果を出している。
0号はそんな記憶から作られた人造人間だ。
そこには「母の記憶」が眠り「母の人格」も眠っている。
もうおわかりいただけただろうか(笑)
ラストの展開はあまりにも驚愕だ、0号とは違う表情、
0号とは違う声で主人公に話しかけて終わるラストは
もうホラーとしか言いようがない。
人造人間を創った一人の研究者は母として息子に
すべてを託し、託された息子は母の手のひらの上で
もう1体の人造人間を作り、そんな人造人間の自我が消えたことで
「母の記憶」が蘇る。
エンドロールですら狂気だ。
エンドロールでアフターストーリー的に
色々なシーンが描かれるのは映画ではお約束だが、
そんなアフターストーリーでさえ狂気だ。
0号が覚えていたはずのことができなくなっていたり、
0号がやらなかった「研究」を主人公の研究室で
母と同じようにやっている姿が描かれる。
母は息子を創り、息子は母を創った。
この作品は狂気じみた「母」の物語であり親子の物語だ。
おそらく彼らは「永遠」の月日を生きるのだろう。
0号の人格はいつか蘇る日が来るのかはわからない、
消えてしまったのか、そもそも0号の人格と呼べるものは
最初から存在したのか。
もしかしたらテーマは創作者のエゴイズム、
親のエゴイズムというものを描いていたのかもしれない。
創作者にとって自身が作り上げたものは子どものようなものだ、
こうあってほしい、こういうふうに育ってほしい、
そんな「エゴイズム」が創作者にも親にもある。
この作品はそんなテーマを描いていたのか、
それとも別のなにかなのか、果たして0号はどうなったのか。
映画が終わったあとに様々な考察を頭の中で巡らせてしまい、
自分の中でそれを整理し、もう1度映画を見たくなる。
非常に挑戦的な作品だった。
総評:とんでもない怪作が生まれた
全体的に見て非常に挑戦作といえる作品だ。
去年はトラペジウムや数分間のエールをやルックバックなど
挑戦的な作品が多かった印象だが、去年のそんな作品に負けていない
とんでもない怪作が生まれてしまった。
序盤はとっつきにくさがあり、中盤も主人公の
身勝手さやサイコパスぶりが目立ち、
終盤も身勝手な行動や台詞が多く、感情移入や共感できるものではない。
だが、それも計算されたキャラクター造形だ。
AIやアンドロイド、人が作り出したものに
「感情」や「自我」は目覚めるのか、この手の作品では
普遍的かつありがちなテーマではあるが、その見せ方が全く持って違う。
一人の天才的な科学者によって生み出された人造人間、
そんな人造人間が人造人間をうみ、互いに傷つけ合いながら
自分自身を、自らの感を、愛を、本物だと証明しようとする。
その展開があまりにもサイコスリラーであり、
終盤の展開は思わず笑ってしまうほど怒涛の展開だ。
少数精鋭かつ新進気鋭のクリエイターだからこそできた
挑戦作であり、有名な監督や大手の制作会社にはできないような角度で
この作品は制作されている。
それゆえに人を選ぶ部分はある。主人公に感情移入などできず、
むしろ苛立ちすら感じる部分もある。
このあたりはラストも含め「School Days」などを彷彿とさせる要素だ。
アニメとしても説明不足な部分もあり、あえてわかりやすくしていない。
見る側が読み解かなければ、きちんと情報を処理しなければ
「わけがわからない」となってしまう作品だろう。
その情報をきちんと処理してもラストはバッドエンドともいえる
部分があり、好みが分かれるところだ。
いい意味でも悪い意味でも作家性というものが大爆発している。
この作品を好きになるか、嫌いになるか。
ぜひ、劇場で確かめてほしい。
個人的な感想:少人数
気軽な気持ちで見に行った作品だったが、
強烈にぶん殴られてしまった作品だ。
しかも、これが少人数で監督含めて8人ほどの
スタッフで制作されているというのも驚きだ。
フルCGという手法だからこそできた部分もあるだろうが、
その欠点を感じさせず利点を感じさせるアニメーションの数々、
荒削りな部分はあるものの「安田現象」という
アニメーション作家の作家性を感じる内容は本当に素晴らしい。
去年くらいからこういった小規模なスタジオの作品も
目立ってきたが、今年も期待できるかもしれないと
感じさせてくれる素晴らしい作品だった。