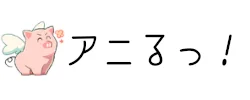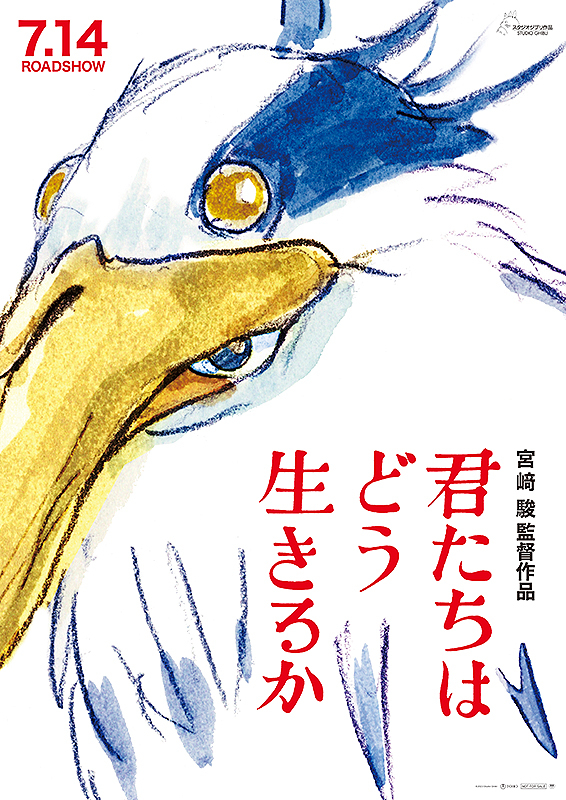評価 ★★★★★(93点) 全124分
あらすじ スタジオジブリ制作の日本のアニメーション映画作品。監督は宮﨑駿。 吉野源三郎の小説『君たちはどう生きるか』からタイトルを取っているが直接の原作とはならず、同小説が主人公にとって大きな意味を持つという形で関わり、物語そのものは冒険活劇ファンタジーとなる。引用- Wikipedia
本作品はスタジオジブリによるオリジナルアニメ映画作品。
監督は宮崎駿。
宮崎駿監督としては風立ちぬ以来、約10年ぶりの作品となる。
なお本レビューはネタバレを含みますのでご注意ください。
群衆
映画冒頭から「これぞスタジオジブリ」という圧巻の作画を見せつけてくる。
主人公の母が入院している病院が空襲で火事になってしまい、
そんな病院に少年の主人公がかけつける。
文章で表現すればただこれだけのシーンだ。
しかし、これだけのシーンを「これだけ」で終わらせないのが
スタジオジブリ、そして宮崎駿監督の凄さだ。
群衆をかき分け、火の熱さを感じながらも、母のもとに駆けつけようとする少年。
聞こえないはずの母の声が聞こえ、火の熱で視線がゆらぎながらも、
群衆をかき分けながら、なんとか母のもとに辿り着こうとする。
そんな事情を知らない群衆はありとあらゆる動きをしている。
火事の方向を見つめるもの、少年を見つめるもの、
一人ひとりが「生きている」ことを感じさせる1枚1枚の作画による
動き、アニメーションとしての魅力がつまりまくりだ。
この冒頭のシーンだけではない、群衆は人だけではなく、
中盤あたりで「インコ」が異世界でひしめき合っている。
このインコは永遠の時の中で進化し、人のように狭い場所で暮らしている。
そんな「暮らし」がほんの一瞬のシーンで本当に細かく描かれている。
酒場のような場所で酒を嗜むもの、家で料理をしているもの。
冒頭のシーンもそうだが、尺としてはそこまで長くない。
たった2,3分の群衆のシーンでこれでもかと描かれまくった作画の中で
一人ひとりのキャラクターの個性と生き様を感じさせている。
ジブリでなければ、宮崎駿でなければできないと
断言したくなるほどのシーンだ。
「風立ちぬ」でも震災のシーンで同じように群衆を描いていたが、
今回はそれ以上に描きこまれている。
映画館なのに一時停止して細かい部分まで見たくなる。
一瞬で過ぎ去るシーンを目に焼き付けたくなる魅力を秘めており、
スタジオジブリの、宮崎駿の世界観に浸れることに
喜びすら感じてしまう。
10年ぶりの新作、82歳になった宮崎駿監督だが、衰えを一切感じさせない。
序盤、主人公の母が死に、かつて母も住んでいた田舎に疎開するのだが、
そんな田舎の家に昔から奉公している老婆達がいる。
「達」である。
私はこの老婆たちが出てきた思わず笑ってしまった。
「宮崎駿」監督といえば特徴的な老婆の描き方が印象に残ってる人も多いはずだ。
ドーラ、カンタのばあちゃん、湯婆婆、ソフィーetc…
印象的な「老婆」が宮崎駿監督作品には多く登場している。
そんな老婆たちを彷彿とさせるような老婆がこの作品には大集合している。
宮崎駿監督作品に出演した老婆たちがゲスト出演しているような感覚だ。
この老婆たちのシーンでも群衆の描き方の素晴らしさが描かれている。
一人をのぞいてキャラの掘り下げはおろか名前はほとんどでてこない。
だが、彼女たちが歩いているシーンだけでどんなキャラなのかを
「見て」感じさせてくれるのだ。
腰が大きく曲がっているもの、ピシッと背筋がのびているもの、
笑顔で歩いているもの、ニヤニヤとしているもの、無表情なもの。
ただ老婆たちが歩いているだけなのに、
その歩いている姿だけでどんなキャラクターなのかが印象づく。
老婆の一人でさえ、脇役ともいえないようなキャラクターでさえ、
一人ひとりが作品の中で生き生きとしており、
それを見る側も如実に感じることができる。
セルフオマージュ
今作はセルフオマージュのようなシーンが非常に多い。
見ていて思わず「あ、この作品っぽいな」
「ここはあの作品をオマージュしてるのか!?」と
一瞬そう考えてしまうようなシーンばかりだ。
例えば映画序盤の日常から中盤の異世界ともいうべき世界に行く際に、
主人公が「樹木のトンネル」を通るシーンが有る。
これはいわずもがな、となりのトトロを彷彿とさせるシーンだ。
更に終盤で「天空の城ラピュタ」でパズーがラピュタの外壁を
上るシーンがあるが、あのようなシーンもこの作品にはある。
そのほかにも「もののけ姫」を彷彿とさせるようなシーンがあったり、
これを「宮崎駿」監督作品だから当たり前と捉えるべきか、
もしくは意識的に宮崎駿監督が自身の作品をセルフオマージュしていると
捉えるべきか悩ましいところだ。
しかし、今作はある種、
宮崎駿監督の「人生」を振り返っていると感じる部分がある。
だからこそ、作品の趣旨的にこれはセルフオマージュであり、
そんなセルフオマージュの1つ1つを見ながら発見する面白さがある。
情報量
本当に1シーン1シーン、いや、1コマ1コマが見逃せない。
序盤からそんなシーンにまみれており、画面に釘付けになってしまう。
非常に情報量の多い作品だ。
宮崎駿監督の中で1番情報量が多い。
その情報量を見ている側が処理しきれるのかが、
この作品の1番の欠点とも言える。
子供であればその情報の処理に追われることなく、
純粋な気持ちで少年の「二人の母」を巡る冒険譚に釘付けになれる。
初期のジブリらしい「日常から非日常への変化」からの
「冒険譚」を素直に子供なら楽しむことができて
ワクワクできるはずだ。
しかし、大人だと色々と考えてしまう。
1コマ1コマに描かれたキャラクターの細かい描写、
セルフオマージュの数々、そして「メタファー」の数々を
読み解こうと勝手に脳が動いてしまう。
その処理におわれてしまい「わけがわからない」作品と
捉える方も多いだろう。
私も見終わった後は脳内の処理におわれてしまい、
必死に脳内に焼き付けたシーンを再生しながら一時停止を繰り返し、
ようやくこのレビューを書いてるくらいだ。
それほど情報量が多い。
2時間という尺の中であえて言葉で解説していない部分も多く、
その解説していない部分、アニメとしては表現している部分を
見る側がどう処理するのかがこの作品のポイントでもある。
見終わった後に「あれはどういう意味があるんだろう?」
「あれはなんだったんだろう?」と考えてしまい、
その答えを自分の中で見つける面白さがある。
どストレートにいってしまえば、この作品は考察アニメだ。
宮崎駿監督作品はそういう要素も少なからずあったものの、
それはあくまで見る側が深読みするからこそ見える部分だ。
しかし、今作は見る側が深読みしていないのに、
考察させるポイントが星の数ほど存在する。
1度見ただけでは飲み込みきれない、
映画館という一時停止できない環境では処理できない情報量の多さが
特徴的な作品だ。
主人公
彼はいい子でいようとする少年だ。
母が死に、その死を受け止めきれていないものの、
疎開がきまり、それだけでなく父は再婚をしてしまう。しかも、母の妹だ。
現代では考えられないような複雑な家庭ともいえる。
だが、そんな複雑な家庭でありながら主人公はいい子でいようとしている。
しかし、子供故にそれもすぐに限界を迎える。
義理の母が自分に優しくしてくれているのに、それを受け入れきれず、
義理の母がつわりで寝込んでいるのにも限らず、そっけない態度だ。
すぐに家庭環境に馴染めるわけがないのは当たり前だ。
そんな態度になってしまう環境に彼は居る。
彼は新しい学校にも馴染めない。彼は「お金持ちの都会の子供」だ。
新しい学校の同級生はみんな坊主頭で、彼のように
シミ1ツない真っ白な服など着ていない。
同級生が家の手伝いをしているのに彼は何もしていない。
非常に恵まれた子供だ。
家に帰れば父は仕事に夢中で、遅くに帰ってくるのを待っていたら、
玄関先で新しい母とキスをしている始末だ(苦笑)
彼は学校でも家庭にも居場所がない。だからこそ、自分で自分を傷つける。
彼は道端でころんだと嘘をつくが、
両親はいじめられたに違いないと勘違いをする、それも想定済みだ。
「心配される」ことで自分の居場所を作ろうとしている。
「嘘」をついたこと、人の「良心」につけこんだこと。
これは悪いことだ。
こんな家庭環境ではそういうことをしてしまうのは納得ではある。
だが、それを彼自身も悪いことだと認識している。
人がもつ「悪意」だ。誰しも少なからず「悪意」はある。
嘘をついたことがない人間など存在しないだろう、
それが人間であり、知恵を持った人間の原罪だ。
家庭環境がかわり、主人公もまたそんな原罪に染まってしまう。
アオサギ
そんな彼の前にアオサギが現れる。
キービジュアルでも描かれている「鳥」がそれだ。
アオサギは主人公の心をざわめかせる。
あるときは母の死に際の言葉を叫び、
あるときは「母が生きている」と嘘をつく。
そんなありえるはずもない「嘘」や彼の心をざわめかせる言葉で、
アオサギは彼を誘おうとしている。
謎のしゃべる鳥の不思議よりも、そんな鳥への苛立ちのほうが勝り、
彼はアオサギに挑もうとしている。
自分で弓を作り、なんとか彼に対抗しようと。
君たちはどう生きるか
そんな苛立ちの日々の中で彼が出会うのが
「君たちはどう生きるか」という本だ。
生前に母が自分に残した本をみつけ、それを読み漁り、
彼の心を動かす。
それにより、彼は自分自身の罪を自覚する。
父にかまってもらおうと嘘をついたことを、
義理の母に冷たく当たってしまったことを。
この時点で彼は成長し、変化している。
それがやや見ている側にはわかりにく、唐突に見えてしまう。
「君たちはどう生きるか」がどんな内容の本なのかは、
作中では描かれることはない。
前述したように、この本を読んでいることも前提としている部分がある。
そんな中で「義理の母」が行方不明になってしまう。
これはある種の「贖罪」だ。
彼はあえて新しい母に冷たい態度を取り、体調の悪い新しい母を傷つけている。
そうすることで彼の心の平穏が保たれるからだ。
しかし「君たちはどう生きるか」をよみ、
わかりやすく言えば改心した主人公は新しい母を救うために動き出す。
誤った行動をしてしまったことは変えられない、
でも、誤りから立ち直ることもできる。
それが彼が母から送られた本を読んで受けたメッセージであり、
母からの言葉でもあると感じたからこその行動だ。
夏子
新しい母である夏子も「悪意」をはらんでいる。
彼女は姉の夫と結婚し子供まで孕んでいる。
それが跡取りのためや世間体、色々な事情が絡んでいるのだろうが、
彼女の「欲望」もあるのだろう。
彼女は主人公に優しく接している。
だが、彼が眠っている顔を「無表情」でなにかいいたげに見つめているシーンが有る。
主人公は実母そっくりな美しい顔をしている。
姉とそっくりな子供、前妻の子供という立場の主人公の顔を見て、
彼女は何を思ったのか。
彼女は中盤、異世界の中で彼に言い放つ
「お前なんか大嫌い!」
これは彼女の本音であると同時に悪意だ。
新しい家族を、姉の忘れ形見を拒絶し、
自分を受け入れてくれない彼を拒絶している。
彼女がなぜ石の塔に訪れたのか。
アオサギや塔の主の思惑もあったのかもしれないが、
もしかしたら時間の流れの違う塔の中で一人で子供をうみ、
育てていこうとしたのかもしれない。
主人公の悪意によって拒絶された彼女もまた、
悪意を持ち、そんな悪意をこれ以上さらけださないために
石の塔という現実ではない世界に逃げ込んでしまった。
そんな悪意に主人公はさらされる。だが、彼は既に改心している身だ。
自分が悪意を持って彼女に接したからこそ、
彼女も悪意に染まってしまった。それを分かっている。
だからこそ最大限に誠意で彼女にそれを返そうとする
「夏子お母さん!」
それまで「おばさん」と呼んでいたのに、
彼はここで彼女を受け入れることを彼女に間接的に伝えている。
自身の誠意をストレートにつたえることで、
彼女のまたそれを受け入れる。
母の「死」を受け入れ、自身の罪を悔いている主人公の成長が
このシーンでは描かれている。
石の塔
石の塔の中は不思議な世界が広がっている。
アオサギに導かれやってきた場所は海に囲まれ、
大量のペリカンが存在し、門のようなものがそこにあるだけだ。
そんな門の前に佇む主人公の後ろから
大量のペリカンがやってきて、門の中へとおしこまれてしまう。
端的に言えばここは「死の世界」のようなものだ。
人が死ねばそこに訪れ、生物を殺すことの出来ない魂のような存在が、
いつしか「ワラワラ」という可愛らしい存在になり、
それが現世にいくことで子供として生まれ変わる。
死者の魂がそこに訪れ、浄化され、転生する。
宮崎駿監督が描く「死の世界」だ。
「ワレヲ学ブモノハ死ス」
門にはそんな事が書かれている。
そんな門をくぐってしまった主人公は漁師のような女性に助けられて、
この世界のことを、常識を、学んでいく。
幻想的で不思議な世界はジブリらしいファンタジックな世界であると
同時に「死」を描いている。
人が死んだらどこへいき、どうなるのか。
この死後の世界では人の魂たる「ワラワラ」を食らうペリカンや、
人そのものを料理にして食べようとするインコも存在する。
これは人の悪意の集合体の象徴だ。
「ワラワラ」は飛んで上の世界に行かなければ転生できない。
だが、ここ最近は飛べずにいる。それは「戦争」ゆえだ。
死者ばかりがこの世界に溢れかえり、生まれゆくものが減っている。
戦争という時代だからこそ、悪意が多く存在する時代だからこそ、
「赤ん坊」が生まれない時代だ。
そんな中で主人公は「ヒミ」と出会う
ヒミ
ヒミは主人公の母だ。
この世界は「時間の流れ」が現実世界とは違う。
ありとあらゆる時代に扉が開かれており、
その扉を通ってヒミは子供時代にこの世界に訪れている。
嘘を言っていたはずの「アオサギ」は嘘をついていない。
彼は一見、嘘をついて主人公を騙しているように見えるが、
アオサギは嘘を言いつつも騙しては居ないのだ。
新しい母もこの世界に存在し、実母もこの世界に生きている。
生きている時代が違うだけだ。
そんなヒミは彼が息子だと最初は気づいていない。
しかし、主人公が徐々に気づいていく。
懐かしい母のパンの味、母の愛に改めて彼は触れることで、
彼はより会心の心を強めていく。
大叔父
この石の塔を立てたのは主人公の大叔父だ。
彼は宇宙から飛来した謎の石の塔にみいられ、建物を作り上げ、
そしていつのまにか姿を消してしまっている。
彼は石と「契約」をしたのだという。
石と契約することで「世界のバランス」をたもち、
この世界をひそかに保ってきた。
しかし、彼も老いている。後継者をずっと探していた。
そのためにアオサギを現実世界に放ち、後継者を探していたのかもしれない。
アオサギが主人公を煽っていたのは、もしかしたらそういう理由なのかもしれない。
このあたりは私の憶測でしかない。
そんな大叔父は後継者として主人公を指名する。
世界のバランスを保つために積み上げてきた積み木、
だが、そんな積み木は悪意に染まってしまっている。
悪意のある積み木をつみたてても、
大叔父と同じような世界にしかならない。
積み木の「悪意」がみえる主人公ならば、
悪意のない世界が作り上げられるはずだと。
拒絶
だが、そんな大叔父の提案を主人公は拒絶する。
彼もまた悪意に染まった人間だ。
それを彼も自覚している、だからこそ彼の提案を拒絶し、
石の塔は崩壊し、世界のバランスが崩れる。
日常から非日常へ、そして非日常から日常へと切り替わり物語は終わる。
世界のバランスは崩れてしまった。
もしかしたら、今後、世界は本当に壊れてしまうかもしれない。
だが「悪意」のない世界を作り上げることは人の手では不可能だ。
どれだけ清廉潔白な人間でも
人は少なからず悪意を持っている。
そんな世界で主人公がどう生きていくのか、それはわからない。
大叔父も勝手に石と契約して世界のバランスを保ってきただけだ。
彼がやる以前にも世界は存在し、彼がいなくなった後も
世界は当たり前のようの存在し続けている。
悪意のない存在を作り上げることなど所詮は人の欺瞞だ。
同時に「この悪意にまみれた世界で君たちはどう生きるか」と
問うてるようなメッセージを感じる作品だ。
人は悪意を放ってしまうものだ、そんな悪意にまみれた世界で、
この作品の主人公のように悪意を自覚し、やり直すのか。
それとも悪意を放ち続ける人間になるのか。
君たちはどう生きるか。
タイトル通りのメッセージを感じ、作品は終りを迎える。
13作品
しかし、これはあくまで表面上のストーリーだ。
この作品の本質は「宮崎駿」そのものといえる。
数々のセルフオマージュシーンの数々は宮崎駿監督の歴史そのものだ。
未来少年コナン、ルパン三世カリオストロの城、
風の谷のナウシカ、天空の城ラピュタ、となりのトトロ、魔女の宅急便、
紅の豚、On Your Mark、もののけ姫、千と千尋の神隠し、
ハウルの動く城、崖の上のポニョ、風立ちぬ。
彼は風立ちぬまでで13作品の作品を監督として作り上げ
世に出してきた。この作品での「大叔父」とは宮崎駿自身だ。
孤独に一人だけで「石」という名の作品を13個積み上げてきてた。
彼自身も老いてきていることを自覚している。
そして後継者をずっと求めていた。
しかし、そんな後継者は結局現れなかったことを
この作品では示唆している。
石との契約により「血縁者」しか後継者に出来ない。
これは「宮崎吾朗」氏に対する思いと無念だろう。
本来は彼を後継者にしたかったのに出来なかった。
そんなメタファーを感じざる得ない。
門
主人公が異世界で最初に目にする門の上にはこんな事が書かれている
「我ヲ学ブ者ハ死ス」
この場合の「我」とは宮崎駿監督自身なのだろう。
監督から学ぼうとし、第二の宮崎駿になろうとしたものたち。
そんなものたちは結局、生まれることもなく死んでいった。
門の上に描かれている意味深な言葉、
シーンとしては1分も描かれてないようなカットで出てくる言葉ですら、
宮崎駿監督自身の嘆きの声が聞こえてくるようだ。
塔の中にいる「インコ」はスタジオジブリのスタッフ、
もしくは我々視聴者なのかもしれない。
大量に存在するインコは大叔父が石の塔の中に入れてしまった結果、
育ってしまったものだ。
しかし、人ざる得ないものであり、あろうことか血縁者である
「ヒミ」と引き換えの権利まで要求してくる始末だ。
だが、そんな権利は通ることはなく、彼の積み上げた積み木を崩してしまう。
彼の世界に取り込まれたインコは人にすらならない
醜悪なものになり、悪意にそまり、人を食らう。
そんなインコもペリカンもラストでは「石の塔」から放たれて自由になっている。
希望
これは宮崎駿監督の嘆きであると同時に希望だ。
自分の作品に、自分の世界に、自分自身にいつまでもしがみつくなという
メッセージのようにも感じる。
石の塔から出れば石の塔の中での記憶はなくなってしまう。
自分が空襲による火事で死ぬ運命にあることがわかっていても
母は笑顔で息子と妹を送り出している。
主人公のポケットには石の塔の「お守り」が入ったままだ。
そのせいで彼の石の塔での記憶はすぐには失われないものの、
いつかは完全に消えゆく。
「スタジオジブリ」作品、宮崎駿監督作品の記憶はいつかは
人々は忘れてしまう、でも、それでもいいんだと言いたげな
メッセージ性を強く感じる作品だった。
総評:宮崎駿の描く死生観と己の人生
全体的に見て、10年ぶりに味わう宮崎駿の世界観に圧倒されてしまう作品だ。
前作もかなり自由に作品を作り上げており、我々視聴者を
あまり意識していないような感じの作品だったものの、
今作は意識しつつも自由に作っている。
圧倒的な作画、圧倒的なアニメーションの魅力は本当に素晴らしく、
そんなクォリティで描かれる過去の宮崎駿監督のセルフオマージュの
数々にニヤニヤしてしまう。
それと同時に情報量が凄まじい作品だ。
あえて説明していない部分が多く、描かれているシーンから
見ている側が「察する」ことを常に求められる。
その処理しなければならない情報の量が異様に多く、
もう1度見なければ完全には飲み込めない、理解できないと思うほどだ。
表面的なテーマ性は人の悪意と誠意だ。
この世界は人の悪意にまみれている、
それをなんとかしようとしても、結局人は悪意を放つ生き物だ。
知恵を持った人の原罪を描きつつ、自分も他人も悪意を持った世界で、
君はどう生きるのかというテーマを描いている。
それと同時に宮崎駿監督自身のことも描いている。
自身が作り上げてきた作品の数々、そんな作品に群がるように
多くの人が集まり、自分勝手に色々なことをしたり、言ってきたり、求めてくる。
そんな中でも彼は孤独に作品を作り上げてきた。
しかし、82歳という年齢ゆえに「死期」も悟っている。
そんな中で後継者が現れなかった後悔も描きつつ、
自身の死後がどうなるのかわからないが、
自分にこだわるなとでも言いたげなラストだ。
これはスタジオジブリ総決算ともいえるが、
私は宮崎駿さんが自身の「生前葬」をしているようにも感じた。
宮崎駿監督の愛弟子でもある「庵野秀明」監督が
シン・エヴァンゲリオンで卒業式を描いたように、
宮崎駿監督の場合はは卒業式ではなく、
自身が生きているうちに自身の作品という形で
生前葬をあげているようにも見えるような作品だ。
見る人によって非常に好みが分かれる作品なのは間違いない。
「宮崎駿」という監督の人生を、作品たちを知らなければ
伝わらない部分がある。そういった意味での「生前葬」だ。
見ず知らずの「生前葬」にいったところで本来はなんの感情も生まれない。
だが、本人が監督した生前葬だからこそ、
飾られているもの、語られているものに、
本人の人生を、宮崎駿監督の場合は作品を、
知っている人ほど突き刺さる。
しかしながら同時に宮崎駿監督の作品が名作であるがゆえに、
宮崎駿という男を知らない人が見ても、
そんな男の過去を振り返るような生前葬でも面白さが伝わってしまう。
それは宮崎駿という天才が為せる技だ。
かつて私達がラピュタや魔女の宅急便を子供心に
ワクワクと楽しんでいたかのように、何も知らない子供のほうが
この作品を純粋に楽しめるのかもしれない。
残念ながらすでに大人になり、悪意にそまった私は
子供のような純粋な気持ちで見ることは出来ない。
いつか私の子供が生まれ、少し成長した時に、
この作品を見せてどう感じるのか、聞いてみたいという
思いが生まれる作品だった。
個人的な感想:フリーズ
見終わった後にちょっと処理に負われてしまう作品だった。
見ている最中でも一時停止!巻き戻し!と劇場のスタッフを
横に縛り付けて指示したくなるほど、一時停止したいシーン、
巻き戻してもう1度みたいシーンが多く、
「劇場」という場所にやきもきさせられてしまった。
本当に圧巻だ。宮崎駿監督の凄さというのを改めて感じてしまう。
初期の宮崎監督らしさ、最近の宮崎駿監督らしさを感じさせる内容であり、
そこに様々なメタファーを詰め込めるだけ詰め込んでいる。
とんでもなく面白いのに、その面白さを私は100%味わいきれていない。
劇場という場所でそれをすることは不可能だ。
BDでじっくりと、何度も見返して、初めてこの作品を飲み込める。
切っていない一玉まるごとのとんでもなく美味しいスイカを
口に詰め込まれるような感覚だ。
一口かじれば甘い実があるのに、
それを覆い隠す皮もとられておらず、サイズもでかい。
でかすぎるがゆえに食べきれない。
そんな感覚を味わうアニメ映画であり、
これを1回で消化し切ることは不可能だ。
風立ちぬを見た後も、劇場ではなく家でもう1度じっくりと見たいと思ったが、
風立ちぬ以上に家でもう1度どころか3度くらい味わいたいと
思ってしまうような作品だった。