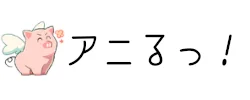評価 ★★★★☆(63点) 全24話
あらすじ 醍醐の国の領主・醍醐景光は地獄堂の十二の鬼神に領土の守護と権力を願うが、代わりに生まれたばかりの息子から体が欠損する。引用- Wikipedia
あゝ無常
原作は手塚治虫による漫画作品。
「どろろ」自体はパイロットフィルム版を含めて、
本作品で三度目のアニメ化となる。
監督は古橋一浩、制作はMAPPA、手塚プロダクション
キャラクターデザイン
本作の企画自体は2016年から始まったようだが、
その中で元々は「手塚治虫」らしいキャラデザと絵の雰囲気で
アニメーションを制作することも考えられていたようだ。
今作では手塚治虫原作と言われなければわからない
渋いキャラクターデザインになっており、どこか時代劇のような雰囲気すら有る。
物語の舞台はいわゆる「戦国時代」だ。
戦乱の世だからこそ、苦しむ民がおり、そんな民が居てもなお
民を配する武将は「天下に名を轟かせたい」と思っている。
そんな武将である「醍醐 景光」は鬼神へと願う。
神ではなく、鬼神へと願ったがゆえに、
己の全てを捧げる願いをした彼の願いは最悪の形で届けられる。
生まれてくる息子の「体」を鬼神へと捧げられ、
そんな子を捨て外道へとおちた父。
生まれてきた子供は「皮膚」すらない。
もはや何故生きているのかわからないその姿は強烈だ。
生きている方が地獄ともいえるいその姿、
捨てられたその赤子は産婆のちょっとした優しさにより
「一命」を取り止めるところから物語が動き出す。
原作のキャラデザは手塚治虫らしい丸みを帯びたデザインをしているが
アニメはそんな丸みを感じさせないキャラデザのキャラが多い。
リアルに、生々しく、現実的に描かれたキャラクターたちがより
この時代だからこその「無常観」を感じさせる雰囲気を生み出している。
全体的に色合いは暗く、重苦しい雰囲気が漂っている。
いつ命が奪われるかわからない、いつ命を失うかわからない。
そんな時代だからこその「どっしり」とした重さが
この作品には漂っている。
どろろ
そんな無常で無情な時代で生きる子供である「どろろ」。
「どろろ」はこんな時代でもたくましく子供一人で生きている。
大人にだろうと懸命に立ち向かうその姿に1話から心を奪われてしまう。
「おいらは誰の指図も受けねぇ、どこにいようがおいらの勝手だ」
この時代の子供だからこその強さ、この時代の子供だからこその
たくましさがあり、だが、同時に可愛らしさも有る。
演じている「鈴木梨央」さんの演技もそんな可愛らしさを後押ししており、
そんな「どろろ」が捨てられた子供である「百鬼丸」、
そして鬼神と出会うことで物語が動き出す。
百鬼丸
百鬼丸は鬼神に体を奪われた少年だ。
そんな彼は鬼神を倒すことで奪われた体を取り戻すことができる。
物語としてはシンプルだ、百鬼丸が各地をめぐり、
各地の鬼神を倒しながら己の身体を取り戻していく物語だ。
序盤の段階では百鬼丸には手もなければ皮膚もなければ、目も耳も、喉もない。
仮面をつけ、腕には刀を仕込み、そんな身体で戦っている。
彼が身体のほぼすべてを奪われた状態からどうしてこんな身体になったのか、
どうして戦えるのか。
本当に徐々に徐々に語られる。
派手なシーンはないものの、まるでドロッとした心の澱を揺らすように
見る側に何かを訴えかけてくる。
原作では「百鬼丸」はテレパシーによる会話が出来たが、
アニメではテレパシーは使えない、リアルだ。
まるで「身体障害者」のように描かれている。
彼は誰とも喋ったこともない、誰の声も聞いたことがない。
原作よりも百鬼丸の設定をより辛辣なものにすることで、
より、この作品の本質ともいうべき部分を
「小林靖子」という脚本家が形作っている。
そんな喋ることも聞くことも出来ない百鬼丸のそばを
「どろろ」は何故か離れない。彼もまた孤独だ。
孤独故に、同じ孤独を抱える「百鬼丸」のそばを離れず、
互いに喋れずとも心を交わしていく。
どろろもまた徐々に、徐々に百鬼丸のことを理解していく。
バケモノにさされようがボコボコにされようが痛みすら感じず、
ただひたすらにバケモノを退治する「百鬼丸」。
原作とは違いテレパシーという交流手段が一切ないからこそ、
より深く「百鬼丸」というキャラが掘り下げられている
感覚
「百鬼丸」という主人公は序盤においては最強だ。
身体は失っていても義手や義足、仕込み刀で戦い、
痛みやおそれを知らぬからこそバケモノ相手にも果敢に立ち向かえる。
しかし、バケモノのを倒せば倒すほど彼の身体はもとに戻っていく。
皮膚や、神経や、感覚。
取り戻せば戻すほど彼には戸惑いが生じる。
生まれて始めて味わう熱さ、生まれて始めて味わう痛み。
私達が当たり前に味わっている「五感」の感覚は
百鬼丸に取っては初めての経験だ。
まるで赤子のごとく初めての感覚を味わっていく描写が生々しい。
痛みを知り、熱さを知り、音を知る。
感覚が蘇るごとに「百鬼丸」は人になっていく。
それは彼に感情を生むきっかけにもなる。
今まで届かなかった人の声、今まで感じなかった痛み、
人と人との交流や身体の「感覚」が人としての感情を作り、心を作る。
感情と心が出来てしまったからこそ「迷い」が生じる。
それは戦いの中でも、旅路の中でも。
迷いは恐怖を生み、恐怖は弱さを生む。
だが、弱さが有るのが人だ。
その弱さを埋めるように「人」を求めていく。
まるで赤子のように「歌」を求め、
この作品は「百鬼丸」という人間の身体と心ができていく物語だ。
奪い奪われる
誰かの何かを奪い、誰かに何かを奪われる。
そんな時代だからこその、それぞれが奪い奪われながらの物語が描かれている。
百鬼丸は全てを奪われた状態だ、だが、彼が取り戻せば取り戻すほど
彼の身体を犠牲に手に入れた「国」が崩壊していく。
鬼神に願った富国強兵。
その果に百鬼丸の父の国は「豊穣」し発展した。
しかし、そんな鬼神に捧げた身体を百鬼丸が取り戻せば取り戻すほど
「国」は疲弊していく。めぐりめぐる因果の物語だ。
百鬼丸は自分自身のために、百鬼丸の父は自身の名声と国のために。
何かを求めれば別の何かを失う。
むしろ、何かを得るためには得るもの以上の何かを失う。
百鬼丸や百鬼丸の父だけではない、この時代で生きるものは
何かを得るために多くの何かを失っている。
身体だけではない、尊厳や、生き方、ときには命を。
戦国の世の、諸行無常がこの作品では描かれている。
多くのものを取り戻していく一方で百鬼丸は多くのものを失っていく。
その代償に彼は「怒り」や「悲しみ」と言った感情も知る。
これまで「鬼神」の命しか奪っていなかった男が、
誰かのために、自分の行き場のない感情を吐き散らかすように人までも殺すようになる。
人は感情を持って初めて人を殺すとでも言っているかのように。
誰かを思い、誰かに怒り、時分が様々な感情をもてたからこそ
他人への思いも生まれる。
そんな百鬼丸の変化を子供である「どろろ」は間近に見ている。
どんなときもそばにいる「どろろ」が百鬼丸にとってかけがえのないものになっていく。
そんな「どろろ」もまた、奪われた子供だ。
両親
百鬼丸は多くを奪われたが、それは取り戻せるものだ。
しかし、その一方でどろろが奪われたものは取り戻せるものではない。
どろろの両親は「野伏せり」、つまりは野盗であり、
彼らもまた生きるために多くのものを奪っていた。それ故に因果応報ではある。
だが、どろろにはそんなことは関係ない。
両親が罪人であろうが、野盗であろうが、どろろにとっては
強い父であり優しい母だ。
奪われたからこそ奪い、奪ったからこそ奪われる。
この時代のどうしようもない世の理の中にどろろも生きている。
どろろは強かった父の面影をどこか百鬼丸に重ねているのかもしれない。
もうひとりにはなりたくない、もう置いていかれたくない。
幼い子供が1人で生きるにはあまりにも厳しすぎる時代だ。
それでも「愛」はある。
父から子供へ、母から子供へ。
そんな「愛」をどろろは受け取っている。
それは百鬼丸にはなかったものだ。
取り戻せるものを取り戻す男と、取り戻せないが失わないもののある子供。
そんなふたりの旅路は続く。
弟
百鬼丸の弟である「多宝丸」は何も知らずに育っている。
自信に兄が居たことも、兄の犠牲で国が反映していることも。
だが、彼は真実を知る。真実を知っても、いや、知ったからこそ悩み答えを出す。
国を守るために、父の意志を継ぐためにも、兄と戦うことになろうとも。
因果だ。
1度、外道に落ち、その果てに得た享受をもう失うことは出来ない。
父も、母も、弟も。
「百鬼丸」の犠牲は必要な犠牲だと、切り捨てる。
この戦国の世だからこその価値観だ。
ときには家族よりも、血を分けた肉親よりも守らなければならないものが有る。
百鬼丸はその言葉を聞き、考える
自身の家族と再会しても受け入れてもらえず、
自身が生きる理由でも有る「鬼神退治」も結果的に民を苦しめることになる。
自身の身体を取り戻すべきか、もうコレ以上、何もせずにいるべきか。
それでも百鬼丸は止まらない。
自身の身体を取り戻す旅は彼の唯一といってもいい生きる理由でもある。
奪われたものを全て取り戻す、そこからでなければ始まらない。
彼はマイナスから始まった存在だ、それゆえに「0」に戻ることに
こだわっている、執念と言ってもいい。その果の犠牲は厭わない。
例え多くの民が飢えようとも、死のうとも。
百鬼丸の生き方は人としての「業」を描いているようだ。
業を深めれば深めるほど人としての道から外れていく、
いずれ百鬼丸もまた妖のごとく、鬼神のようになるかもしれない。
百鬼丸の身体はどんどん、どんどんと血に染まっていく。
丁寧なキャラクター描写と言葉の少ない百鬼丸の心理描写を
さりげない「表情」や仕草、少ない言葉で描いており、
台詞が少ないからこそ、1つ1つの台詞に重みが生まれている。
1話では喋ることすら出来なかった少年が、17話では
己の生きる意味を少ない言葉で語らせる。
2クールというストーリー構成だからこそ、
1話1話丁寧に積み重ね、その中で描かれる因果と業が
一人ひとりのキャラクターの中でくすぶり、
無常観あふれる作画がこの作品を彩っている
どろろと百鬼丸
誰も彼を救ってはくれない。だが、彼のそばには「どろろ」がいる。
それが彼を唯一、人たらしめているものだ。2人の関係性は儚く尊い。
最初は互いの名すら知らず、言葉すら交わしていなかった。
だが、そんな2人が言葉をかわし、心を交わし、
額をくっつけ合う姿に涙腺が刺激されてしまう。
全てを受け入れ覚悟し、どろろを守ることを決めた百鬼丸は
己の両足で立ち上がる。
例え自らの弟であろうとも、自らの身体を取り戻すために彼は戦い続ける。
それは「どろろ」という存在を守るためのものでも有る。
彼には守らなければならないものが出来てしまった。
それは彼の弱さであり、生きる理由でもあり、未来だ。
感覚を取り戻し、体を取り戻し、五感を感じ、人の心を感じ、愛を知った。
だからこそ彼は「人間」になりたいとより強く願うようになってしまう。
身体を取り戻せば取り戻すほど「失う」ことが怖くなる。
百鬼丸にとってどろろは全てだ。俺の身体以上に大切な存在だ。
それ以外は家族ですらどうでもいい。
そんな百鬼丸に、両親を失ったどろろは悲しげな表情を浮かべる。
最初は一言も喋らなかった「百鬼丸」、
彼を演ずる「鈴木拡樹」の演技も話が進めば進むほど凄身すら感じさせる。
心を得たからこその、心の叫び。
「返せ!俺の身体だ!」
その身が赤く染まれば染まるほど心は鬼へと化していく。
どろろを己の目でみるために、己の手で触るために。
愛する人を見たい、触れたいという純粋な想いだ。
声を聴くことはできる、喋ることもできる。
だが、見ることも、触れる感触を味わうことも出来ない。
多くのものを取り戻したからこそ欲は深まり、業は深まっていく
そんな業の深さを表すように戦闘シーンはより激しく描かれていく。
序盤はどこか淡々とした戦闘シーンも多かったが、
人と人の戦いが描かれると、この作品で描きたいのはそこだと言わんばかりに
激しい剣戟が描かれる。グリグリと動くアクションはさすがはMAPPAだ。
修羅の道へと落ちた百鬼丸、鬼神の力を得た多宝丸。
終盤の展開の「えげつなさ」は凄まじい。
誰しもに戦う理由があり、それを強く否定できない。
見ている側の心をえぐり、どんな展開になるのかもまるで予想できない。
原作からの改変点はかなり多い。
だが、改変したところにきちんと意味がある。
なぜ百鬼丸の両腕と目は終盤まで戻らなかったのか。
その答えをえげつない形で見せつけてくる。
もはや妖かしとの戦いではない。人と人の、業のぶつけ合いだ。
母
全てを取り戻した百鬼丸が見た姿。
それは「2人のおっかちゃん」だ。
本当なら生まれた赤子が初めてその目で見るもの、
ようやく、百鬼丸が全てを取り戻した瞬間は涙なしには見れない。
やっと百鬼丸が生まれた瞬間だ。
因果の節目を終え、ようやく生まれたからこそ、
彼は自分自身を確かめる。
ハッピーエンドともバッドエンドとも言えない。
原作のどろろは未完だ。
そんな未完だからこそのエンディングは
この物語のラストは見るもの心に何かを残し、
想像を書き立たせてくれるシーンでこの作品は終わる。
総評:これぞ小林靖子
全体的に見て脚本を手掛ける「小林靖子」さんのテイストを強く感じる作品だ。
原作のどろろは未完だ、百鬼丸と同じように完璧な作品ではない。
そんな未完な作品だからこそ実写映画化や、小説、
多くの漫画家による作品も生まれている。
そんな「どろろ」という未完の作品だからこその小林靖子節だ。
原作からの改変点は多い。その改変点の多さは気になるところでは有るものの、
このラストにつなげるための展開であることを考えれば納得できる。
2クールという尺故に減らされた鬼神の数、
テレパシーが使えない百鬼丸、取り戻す身体のパーツの順番。
全てはこの作品が持つ「無常観」と「人間の業と本質」を描くためのものだ。
終盤はもはやほとんど鬼神や妖かしと言える存在は出てこず、人間同士の争いだ。
そもそもこの戦い自体も百鬼丸の父が鬼神に願わなければ起きなかった出来事だ。
それもまた人間の業であり、そんな人間の業から始まった物語は人間の業で終わる。
容赦のない展開の数々とキャラ描写の数々はまさに
「小林靖子節」を感じる脚本に仕上がっており、
そこにMAPPAが手掛ける作画がこの作品の雰囲気を後押しし、
終盤の剣戟は目を離すことなど出来ないシーンに仕上がっている。
演じている声優さんの演技も素晴らしく、
どろろの演技は最初こそどこか素人っぽさを感じたが、
話が進んでくるほど上手くなっていき、どろろのキャラ描写をより深いものにし、
序盤はほとんどしゃべらない百鬼丸の序盤と終盤の演技の違いは
より百鬼丸というキャラに感情移入させてくれる演技だ。
決して明るい話ではなく、どんよりとどっしりとした作品だ。
グロとまではいかないまでも人体破損の描写も多く、
人によっては受け付けない作品だろう。
「どろろ」という作品に思い入れが強いと受け付けない人もいるだろう。
だが、それでもこの作品は名作だ。
原作の手塚治虫が手掛けたテイストと本質は残しつつ、
昭和の未完の名作を令和で「小林靖子」節全開で完結してくれた作品だ。
個人的な感想:原作
原作を読んだのはだいぶ昔で、印象としては実写映画のほうも強いのだが、
そんな中で見たからこそ逆にちょうどよかったのかもしれない。
原作改変部分は非常に多く、いい意味で原作とテイストが違う部分もある。
私はそこも楽しめたのだが、気になる人はいるだろうなと
強く感じてしまう作品でもあった。